第十の堰物語 2004年4月8日更新(堰遊びマップ追加) 吉野川下流と第十堰。徳島平野は吉野川の氾濫がつくった沖積平野であり、徳島市内でたくさんの川が縦横無尽に流れる。第十堰は、吉野川の屈曲点に置かれた構造物で地勢的にも重要な構築物であることが伺える(↑クリックで拡大)。 |
|
 (子どもが自転車で堰を渡っていく。夏真っ盛り…) (子どもが自転車で堰を渡っていく。夏真っ盛り…)二五〇年余りにわたって吉野川に溶け込んだ構造物がある。第十の堰である。当時の第十村にあったことからこう呼ばれる。この堰は農業用水確保のため、江戸時代中期に作られたものである。 石積みの景観は周囲に溶け込んでいて、付近は魚介類や野鳥の宝庫である。往時は、青石を積んだ堰の上を水が越えていき、その流れに乗ってアユやウナギがたくさん上っていった。 阿波十二景の一つ「激流第十の堰」と記された昔の絵はがきには、満々と水をたたえた川面に白帆を立てた川船と、堰の南岸の浅瀬に仕掛けられたヤナが澄んだ水底の石ころとともに映し出されている。 「ここに立ったら、気持ちがすうっとするわ…」  (向こう岸まで歩いて渡ってみれば楽しい) (向こう岸まで歩いて渡ってみれば楽しい)人々は土手の上から、広々とした風景を眺めていた。堰は、子どもたちの恰好の水遊びの場所であり、仕事が終わった大人たちは夕涼みがてら四方山話を咲かせたという。石積みの柔構造のため、大水が来れば補修は必要だっただろうが、地域の人々の手によって二五〇年にわたって維持されてきた。 しかしそのために、上流と下流の水の循環、物質の循環、生態系のつながりが妨げられることなく自然に溶け込んだと考えられる。維持管理に地域の人々がかかわることで、川との密接な結びつきが生まれ、川を知ることにつながった。経済的にも地域に資する仕組みとして参考にならないだろうか。  (1年ほど前に発見された青石を敷きつめた場所) (1年ほど前に発見された青石を敷きつめた場所)第十の堰を在所とする尾上一幸さんはこう回想する。 さくら、菜の花、れんげの咲く頃は人生の節目の時であった。丁稚奉公や入隊が決まった子どもを親がわざわざ堰まで連れてきて、「これがお前の故郷ぞ」と見せていた光景を思い出す。カメラが普及していなかった時代は、それがせめてものことであった。 春が過ぎる頃、子どもたちは川に入り、魚とりが始まる。ハエナワのエサは竹林から取ってきたミミズである。仕掛けた夜はどんな魚がかかるか楽しみでなかなか寝つけなかったものだ。竹林は洪水を防ぐために植えられたものだが、たけのこや釣り竿の調達場所でもあった。  (巨大なソウギョもいる堰直下流の淵) (巨大なソウギョもいる堰直下流の淵)夏休みともなれば、子どもたちは毎日のように堰に泳ぎに来た。遊泳区域も学年や身体の大きさによって自然に決まっていた。小学校低学年は、浅瀬のある堰の上部で、少し高学年は向こう岸まで、高等科になれば、堰のうず巻く流れをどう泳ぎこなすかというようにである。水が澄んでいたので川底まで見透せ、アユ、イダ、ヨシ、ドブロク、アユカケなどが泳いでいるのが見えた。カニもいっぱいいて、堰は淡水魚の宝庫であった。 子どもたちはひと夏を過ごすと、身体が日焼けしてたくましくなる。上級生の指導によって向こう岸(二百米) まで泳げた時の感激はひとしおであり、夏が終わるころには自慢話に花が咲いた。子どもは泳ぐことによって成長していく。 当時は、堰の表面に水の流れはなくとも、積み石と積み石のすき間から水が流れ出ていた。その流れ込む水の音を堰の音ととらえ、梅雨や台風時の水量を音によって聞き分けてもいた。堰の表面に水が流れるようになれば、上流に雨が降ったと予測し、それによって農作業への気配りもできた。  (水面を見ているだけで癒される) (水面を見ているだけで癒される)お盆の夜の食事には、八つ頭の酢あえ、素麺、茄子の味噌あえ、五目ずしなどが出された。自分で捕ってきた鮎の姿ずしは最高の味であった。食事の後はトマトや西瓜も出され、家族全員が今年も健康で先祖の供養盆ができたことを喜び合った。 早米の稲穂が出る頃は、台風の時期でもある。笛や太鼓の音が秋の夜長に聞こえてくると、祭礼の準備が始まる。台風の被害を受けずたわわに実った稲穂を見て、百姓の喜びを感ずる。豊作はうれしかった。祭りのご馳走といえば何といっても糀で造る甘酒だ。すっぱさと甘さがかみ合った独特な味は忘れられない。 一方、堰は落ち鮎の季節である。落ち鮎はあまり美味とは言えないが、豊漁となってどこの家にも鮎を焼く香りが立ち、秋の訪れを感じた。学校から帰ると蒸したサツマイモやサトウキビをおやつに食べ、神社に集まって遊んだ。  (堰全体が魚道となり、アユが上っていく) (堰全体が魚道となり、アユが上っていく)十二月に入ると、水量の減った川で堰の補強工事が始まる。何台もの荷馬車によって、水が引いた堰の上にトロッコの線路が敷かれ、ふもとの山から青石が運ばれた。青石をトロッコに積むのを見にいくのが何より楽しみであった。 堤防での雑草の野焼きは壮観である。大勢の子どもが集まって、西の方から火をつけると、西風に煽られ大きな火柱が立ち、みるみるうちに拡がっていく。 冬の吉野川は、五米くらい川底が透けて見える。野焼きの消火に汗だくとなった顔や手を洗うとき、ついでに口の中も川の水ですすぐくらい、きれいな流れであった──。  (飲めるかも…との噂。上堰の付け根の湧き水) (飲めるかも…との噂。上堰の付け根の湧き水)河口から約一四キロにある第十の堰直下は、川と海が出会う場所でもある。今も昔も子どもの姿は絶えることはない。盛夏と晩秋の堰を覗いてみよう。 → 吉野川シンポ実行委による第十堰マップ(遊びどころがわかります) 八月の堰 自然観察会が行われた第十堰。野鳥や植物の専門家の話を伺ったあと、地元の漁師さんの案内で下流の船上から堰を眺める。堰の上を水が越えていく様子は、青石を積み上げた往時をしのばせる。 やがて船は中州にたどりついた。水底の石がひとつひとつ数えられる。水が澄んでいるのは、堰本体という天然の浄水器をくぐりぬけた水が下流に湧きだしているからだろう。喜んだ子どもたちは、帰りの船が来ても水から上がろうとしない。 中州は北岸から泳いで渡ることもできる。島にヤナギが一本生えていて、水面に影を落としている。恋人たちの避暑地、少年の隠れ家ともいえるような秘密めいた感じがする。  (河口からわずか14キロ。この澄んだ水はなぜ?) (河口からわずか14キロ。この澄んだ水はなぜ?)秋の第十の堰 澄んだ水、沈んだ流木、陽光が射し込める水底は珊瑚礁のよう。あまりの美しさに居合わせた人たちは声が出なかった。幸運にも第十の堰の潜水に同行させてもらった一日である。 時は大潮の干潮の時刻。船は堰本体に沿って進む。ところが不思議な現象に気づいた。堰直下の川面では、水割りウィスキーのごとく水がゆらめいている。この現象はどこでも見られるが、魚道のない南岸の方が見やすい。 一方北岸は魚の宝庫である。1メートルもあるソウギョが岸辺近くを悠々と泳いでいる。南岸は海水が入ってくるが、北岸は引き潮時にはほとんど真水となる。夏に訪れた時も水底の美しさに驚いたが、水が澄んだ今の時期は息をのむほどである。そして堰直下の苔のついていないさらさらの砂…それは天からこぼれた銀の砂のよう。早明浦ダム下流でこれほど美しい川底を知らない。堰を通過する水が運んでくるのかもしれない。 引き潮を選んで、第十の堰の水際を散策してみよう。この感動は体験してみなければわからない。  (堰という天然の浄水器を通過した水たち) (堰という天然の浄水器を通過した水たち)十一月というのに、子どもが十人ばかり泳いでいるではないか。手に手に網を持ち、パンツ一枚で潜って魚を追い込んでいる。追われる魚はというと、アマゾンで見かけるような巨体をくねらせて泳いでいる。ここはほんとうに徳島なのかとびっくりさせられる。  (石ころをみれば川が生きていることがわかる) (石ころをみれば川が生きていることがわかる)第十の堰は、もともと竹の籠に石を詰め、その上に地場の青石を積んだもので、堰の上を水が滑るように越えていき、その一部は伏流水となって下流に湧き出す。 そのため、清流に生息するアユカケという魚や、生態系ピラミッドの頂点に位置するタカの仲間ミサゴも棲んでいる。このことは、餌となる小鳥や魚が豊富であり、さらにその餌となる小さな魚介類やプランクトンが豊富なことを示す。近年では、イセウキヤガラという貴重な水辺植物の日本最大の群落も発見された。また、シジミの産地として潮干狩りの人で賑わう。  (水が出れば釣り人が集まってくる。川の営み) (水が出れば釣り人が集まってくる。川の営み)人間が堰を造り、川は堰に対して抵抗する。第十の堰は、地震や大水、流路の変遷などの自然環境や社会条件の変化にも柔軟に対応しながら、その時々に応じて堰が延長されたり補強されたりして少しずつ今日の形になった。それを下関大学の坂本紘二教授は「成っていく構造」と呼ぶ。「人工物でありながら、自然に同化しているのが最高の技術である」とも言う。  (堰を舞台に「月の音楽会」とは…) (堰を舞台に「月の音楽会」とは…)第十の堰とは、人が川とかかわりながら、持続的に存続させていく仕組みであり、未来に継承していける絶妙の資産なのではないか。二五〇年の歴史がそのことを証明している。 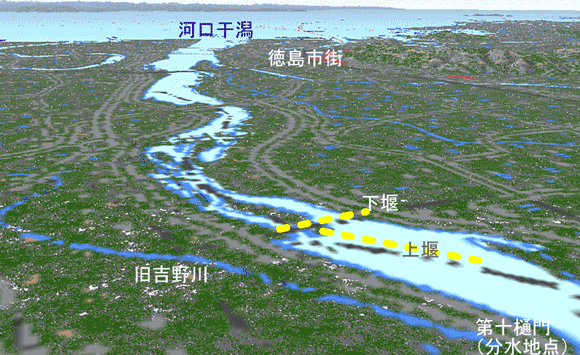 ▲戻る Copyright(c)1999-2000 Yoshinobu Hirai, All Rights Reserved |